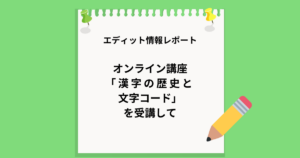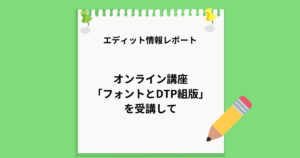オンライン講座「期待されるアフターコロナの編集者像」
講師:中村由紀人(なかむら・ゆきと)氏
【講師略歴】
PHP研究所で30年間、出版営業を皮切りに、雑誌編集、書籍編集、電子書籍そして新規事業を担当。その後、Panasonicとの合弁会社のメディアライツへ経営責任者として、8年間出向。復帰後はデジタル事業とライツ事業を推進。PHP研究所退社後、毎日新聞出版株式会社・取締役を経て、現在は毎日新聞社・社長室委員、日販IPS株式会社のアドバイザーも務める。
中村由紀人さんの講演は、2017年5月に引き続き、2度目です。前回の講演のタイトルは、「時代が求める編集者の役割とは」でした。
コロナ禍の中で、いろいろなことが起きています。出版界にも勝ち組と負け組ができているようです。そして、そこでは新しい編集者の像がだんだん明確になってきているようです。
今回の中村さんの提言は、出版界のDX(Digital Transformation)の流れの中で、特にPOD(Print on Demand)を中心にして、いま何が起きているのか、そして、その中で編集者の役割とは何かを明確にして、アフターコロナの時代の編集者の新しい第一歩を期待したものと思われます。そして、新しい出版のあり方の提言でもありました。
講演の内容を簡単に紹介します。
講義内容
-
コロナ禍で起きた出版業界の動き
- 巣ごもり状況の中で、出版界のDXの進行に伴い、業界が勝ち組と負け組に分かれた。
- コミックBIG4(KADOKAWA、講談社、小学館、集英社)が増収増益に。
- メディアドゥが、トーハンの筆頭株主になる。
→メディアドゥの株式は下落したが、今後の動きは注目する必要がある。
-
コロナ禍で加速する業界の変化
- 加速する出版活動のオンライン化
→発刊書籍の削減と延期、書店訪問の禁止、在宅勤務、イベントの中止。 - 出版社のインプリント化による格差と分断
→大手出版社が中小規模の出版社を買収し、レーベルを残したまま傘下に。 - 出版流通で“中抜き”の動き
→通販の産直市場が拡大する中、問われる取次店の使命と役割。 - 業界を超えた”大競争時代”の到来
→異業種からの出版事業への参入、異業種からの投資や競業で生き残り。
- 加速する出版活動のオンライン化
-
自分自身でデビューする時代
- 芸能プロダクションやレコード会社からデビューしていたタレントが、今ではSNSなどを使って、一人でデビュー(ユーチューバーなど)。
- POD、出版倉庫会社の支援のもの、1部から出版できるようになって、新しい作家の誕生の可能性も生まれる。
-
出版社という存在は必要かどうか
- PODは、①市販の書籍に比べて見劣りがする、②オフセットと比べると原価が割高、③ぺーパーバックしか対応できない、④リアル書店には並ばない、などと言われていたが、これは都市伝説になった。
- 新しい技術の出現に人は懐疑的になるが、PODでも、カバー、帯付き、上製本が可能であるし、ISBNコードを取得して、書店と直取引もできるようになっている。編集費だけはいっしょだが、その他は激安になっている。
- 中村由紀人さんが、コロナ禍で、ZOOMで打ち合わせ、取材してPODで出版した本の紹介。
→一度もリアルで会うことなく出来上がった出版物。- 『はじめての認知症ケア』病院の出版社・テネット(医療法人社団自靖会)
- 『最後の弟子が松下幸之助から学んだ経営の鉄則』(フォレスト出版)
- 『「改革」のための医療経済学』(北東亜洲出版)
- 毎日新聞の出版社・思い出ブックス
- 編集者は不滅である。
→本を出版するためには、必ずしも出版社を必要としない時代が到来した。
-
アフターコロナの編集者の条件
- 社員から個人事業主を目指す。
→出版社の編集者は45年定年、プロダクションの編集者は暖簾分け、こうした人たちを、下請けではなく、パートナーとして活用すること。 - 編集者の人脈は作家だけではない。
→著者たちの人脈が財産であるのは当たり前だが、外部スタッフの人脈がそれ以上に大切。 - 目の前の仕事の理解だけでは足りない。
→「川上」と「川下」の仕事を理解することで、プロに近づく。出版全体の仕事を知ること。 - デジタルとライツは必須の知識、新しい技術で自分の時間をつくる。
→わからないことは“グーグル先生”に聞く。 - 業界情報の(動き)を知っている。
会社で購読の“業界紙”やネット情報でインプット。
- 社員から個人事業主を目指す。
感想
出版ということを考えるときには、内田樹が『街場のメディア論』で述べていましたが、文化としての出版と商品としての出版とを区別して考える必要があると思います。つまり、本というものを文化として考えるか、商品として考えるかということです。もちろん資本主義社会においては、あらゆるモノは商品化されて存在するので、自分以外の他者の使用価値として存在するモノは、商品として存在することになりますが、それでもこうしたアプローチは有効だと思っています。言い換えれば、同じ本といっても、二つの側面を持っていると考えることが、出版を考えるときには大事だということです。売れなくなったら、それでおしまいと考えるのは、本を商品としてしか、考えていないということです。このことは、学校教育が資本主義社会の中で教育サービスを売っているという形態をとっていても、児童生徒を単なる消費者として学校に行っていると考えるだけではいけないということと同じです。
売れる本をどうしてつくるかという問題は、本を商品としてたくさん売れるようにするためにはどうするかということです。文化としての本を考えるときは、売れなくてもいいから、たくさんの読者に読んでもらいたいということを考えていることになります。たくさんの読者に読んでもらえるというのは、売れるということではないのかと考えられますが、デジタル時代では、それは、商品として売れるということとイコールではないということがより明確になってきました。中村さんが問題にしている「新しい技術」ということを考えた場合、ここのところがポイントになってきます。ユーチューバーは、多くのヒトに見てもらえることで、利益をあげています。それは、広告の存在に依存しています。本のように1冊いくらという定価がついていて、たくさん売れるとたくさんカネが入ってくるということとは少し違います。たくさんの人に見てもらえるということは、それだけで価値があることでもあります。つまりたくさんのフォロワーがいるということは、Web上では、存在価値があるということです。「note」などのような、小説や、コミックなどの投稿サイトの存在は、YouTubeに似ています。
PODは、どちらかというと、文化としての出版ということを考えるときに最適だと思われます。大学の教授がテキストとして使う教科書としての本は、商品であるというより、文化としての出版と考えたほうがいいと思います。それは、たくさん売るという発想でつくられているわけではないからです。著者の思想や考え方などを普及するためにつくられているのだと思います。そういう本は、現在は売れない本ということで、出版社から敬遠されています。PODの最大の特徴は何かというと、本は、商品としてたくさん売れなくても出版することができるということだと思います。もちろんビジネスとしてPODを考えた場合は、損をしない(編集者の労力に見合った利益を出す)ことが必要であり、それが持続性を保障することになります。
紙の本でベストセラーを出すということ、とくにミリオンセラーを出すことは、本当は環境破壊につながることでもあります。もしそれがすべて電子書籍であったなら、紙や物流は不要であり、資源の節約になるはずです。これは、最近はやりのSDGsということから考えるととてもベターなことです。しかし、それは、商業出版業界にとってはあまり嬉しいことではないようです。もちろん読者が紙の本を選択するということが前提にありますが、……。
私は、コミックが電子書籍として売れているということは、とてもよいことだと思います。コロナ禍の中で売上増のBIG4(KADOKAWA、講談社、集英社、小学館)は、電子書籍と著作権で利益を出しています。ただし、最も売れる商品が、紙や物流を不要にしているのは、ただでさえ雑誌などが売れなくなって、取次による出版物流が壊滅的な事態になっているのを、さらに推し進めることになっています。今後の取次の課題は、明らかに、少部数の書籍の書店流通をどう効率的に実現していくかにあります。中村さんの情報によれば、メディアドゥと出版社大手が組んで、新しいコミックの流通の仕組みを考えているらしいですが、このことは従来の取次にとって、更なる脅威だと思われます。トーハンの筆頭株主のメディアドゥがどのように考えているのかは興味深い問題です。
中村さんが、出版社がなくても本が出版できるというとき、本当は、編集者の可能性の広がりと同時に、新しい文化としての出版の可能性も意味していると思いました。中村さんが、コロナ禍の中で、リアルの世界では一度も著者に会わずに、本を出版した例を4つほど紹介されていますが、普通の商業出版の世界では、実現不可能な本を、編集者の力で世に出し、最後は、商業出版の世界でも取り上げられるというのは、とても素晴らしいことだと思いました。出版の技術の進歩によって、編集者がこれはどうしても多くの人に読んでもらいたいと思う本を世に出す方法の選択肢は、とても多くなってきたのだと思います。中村さんの例は、はじめは、多分、自費出版の応援として始められたのだと思われますが、それなりに、ビジネスにもなってきています。
中村さんの提言を、私たち、編集プロダクションとしては、編集者の役割を見直し、新しい仕事にも結びつけられる可能性の提案として、じっくり考えていくべきだと思います。大手の出版社だけが生き残るのではなく、多様なメディアとして、いろいろな出版のあり方が実現できることは、文化としての出版の存続としても大切なことだと思います。出版社としても、今までだったら増刷ができないので絶版になってしまうという本でも、PODを使うことによって、少部数でも出版でき、読者に読んでもらえることが可能になってきています。デジタルになっていれば、さらに、いつでも読めることになります。
本の価値は、消費者というより、読者が決めるものだと思います。そのためには、取り敢えず、本として出版しないことには、読者に巡り会えません。本には、デジタルもありますし、紙の本もあります。読者が読むことができるための新しい技術の出現には積極的に挑戦すべきだという中村さんの提言が、心に響きました。
- 参考文献
- 内田樹著『街場のメディア論』(光文社新書/2010.8.20)